Wallace Stevens
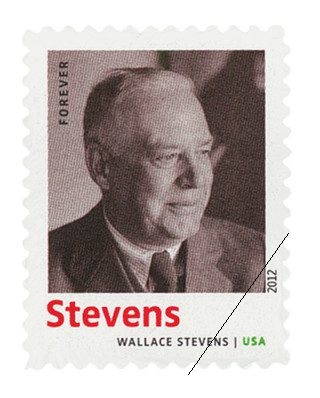
ウォーレス・スティーヴンズ(Wallace Stevens, 1879年10月2日 – 1955年8月2日)は、20世紀アメリカを代表する詩人のひとりであり、モダニズム詩の重要な存在です。彼は職業詩人ではなく、長く保険会社の重役として働きながら、並行して独自の詩作を展開しました。そのため「昼は保険会社の幹部、夜は詩人」という特異な経歴を持つ人物としても知られています。以下では、生涯・詩風・思想的背景・評価について順に解説します。
生涯
スティーヴンズはペンシルベニア州レディングに生まれ、ハーバード大学で学んだのちニューヨークに移り、ジャーナリズムや弁護士補助を経て保険業界に入ります。1916年以降はハートフォード・アクシデント・アンド・インデムニティ社で勤務し、後には副社長となりました。つまり彼の生活の基盤はあくまで企業人としての安定した職業にあり、詩はその並行活動として書かれ続けたのです。
詩人としての本格的な評価は比較的遅く、1923年に刊行された最初の詩集『ハーモニウム(Harmonium)』によって注目を集めました。この中には代表作「十三の方法で鳥をみる(Thirteen Ways of Looking at a Blackbird)」や「日曜日の朝(Sunday Morning)」が含まれています。以後、生涯にわたって詩集を発表し続け、晩年の『The Collected Poems of Wallace Stevens』(1954)でピューリッツァー賞を受賞しました。
詩風と主題
スティーヴンズの詩は、自然・想像力・現実の関係をめぐる哲学的な問いを特徴とします。難解さ、抽象性、音楽的なリズム感がよく指摘されます。彼の関心はしばしば「神なき時代における美と意味の探求」と表現され、宗教的信仰に代わるものとして「想像力」の力を強調しました。
たとえば「日曜日の朝」では、キリスト教の伝統的な来世観を退け、むしろ現世の自然と感覚において美を見出す態度が示されます。また「雪の男(The Snow Man)」では、世界を無私の視点から見ること、つまり主観を脱ぎ捨てて「無」の冷たさを見つめる感覚が表現されています。
スティーヴンズはモダニズム詩人の中でも特に「現実と想像力の対話」を徹底して掘り下げた詩人であり、そのため一見難解に見えながらも、独特の鮮やかなイメージと哲学的思索が結びついています。
思想的背景
彼の詩には哲学的背景が強く、アメリカ実用主義哲学(ウィリアム・ジェイムズやジョン・デューイなど)や、同時代のヨーロッパ思想(ニーチェ、フッサールなど)と響き合う部分が指摘されます。スティーヴンズにとって「想像力」とは単なる空想ではなく、現実を形づくり意味を与える力でした。神の権威が衰退した20世紀において、人間がどのように意味と秩序を見出すか——この問いに対する彼の答えが「想像力の行使」だったのです。
評価と影響
スティーヴンズは同時代には一部の文学者や批評家にしか読まれませんでしたが、死後に評価が急速に高まり、現在ではT・S・エリオット、エズラ・パウンド、マリアン・ムーアらと並んでアメリカ・モダニズム詩の中心人物とされています。彼の詩は文学のみならず、哲学や美学の分野でも広く研究対象となっており、「詩人にして形而上学者」と評されることもあります。